新車・中古車の購入やカーリースを活用したマイクロ法人・フリーランス向けの節税大全
- Home
- フリーランスの資金術
- 新車・中古車の購入やカーリースを活用したマイクロ法人・フリーランス向けの節税大全
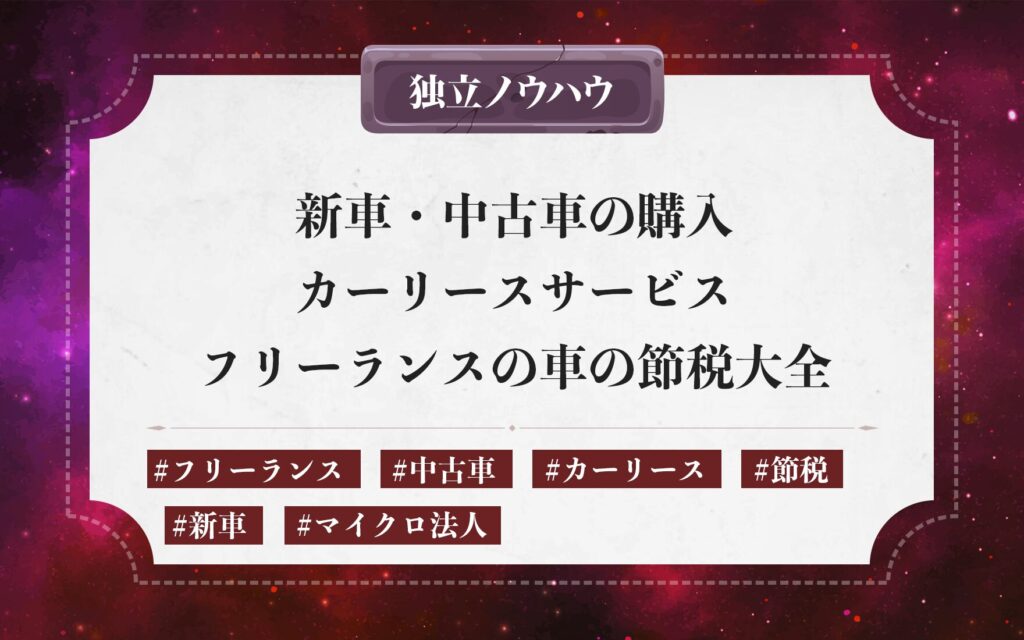
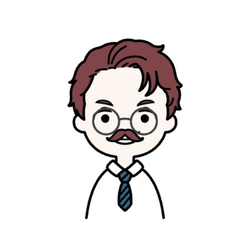
フリ転編集部 山脇
大手新聞社で編集オペレーターを務めた後、奈良日日新聞社に入社し、制作課主任として編集業務全般(紙面組版をはじめ、記者・広告制作、デザイン業務など)に従事。休刊後はフリーランスとして本格的に活動を開始し、新聞組版のほか、地方紙やウェブメディアでの原稿執筆も行う。
個人事業主やマイクロ法人にとって、車は重要なビジネスツールです。しかし、単なる移動手段としてではなく、適切に経費処理を行うことで節税にもつなげることができます。
一方で、車の取得方法には「購入」と「リース」があり、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で最適な方法を選ぶ必要があります。本記事では、車を活用した節税方法に加え、「購入」と「リース」どちらがおすすめなのかについても詳しく解説します。

車の取得方法を正しく選べば、節税効果を最大化できます。長期使用なら購入、初期費用を抑えたいならリースが最適です。維持費も適切に経費計上すれば、無駄なく節税できます。事業スタイルに合った方法を選び、資金繰りを安定させましょう。
目次
車の取得費用と減価償却 一括経費化は可能?
車の取得費用は経費になる?
事業用の車を購入する場合、その取得費用は経費になります。ただし、一括で計上することはできず、「減価償却」によって数年にわたって経費化する必要があります。
車の購入費用には以下のようなものが含まれます。
| 項目 | 特徴 |
| 車両本体価格 | 車そのものの購入価格。経費として計上可能 |
| オプション | カーナビ、ETC、ドライブレコーダーなどのオプション費用。これも経費として計上可能 |
| 納車費用 | 車の納車に関する費用(運搬費用など)。経費として計上可能 |
| 登録諸費用 | 自動車税、重量税、取得税などの登録に必要な費用。経費として計上可能 |
| リサイクル料 | 車のリサイクルに関わる費用(リサイクル料)は、経費計上できず、資産計上する必要がある |
ただし、「リサイクル料」は経費計上できず、資産計上となる点に注意が必要です。
減価償却の仕組みと耐用年数
減価償却の定額法と定率法
車両の減価償却には、「定額法」と「定率法」の二つの方法があります。どちらを採用するかは、税務署のルールや事業主の節税戦略に基づいて決まります。
定額法は、車両の取得価額に対して毎年一定の金額を償却する方法です。具体的には、車両の取得価額を法定耐用年数で割り、その金額を毎年経費として計上します。例として、新車の普通車を600万円で購入し、法定耐用年数6年を選んだ場合、毎年100万円を経費として計上します。
一方、定率法は車両の帳簿価額(取得価額から既に償却された金額)に一定の償却率を掛けて償却費を計上する方法です。最初の数年間で多くの経費が計上されるため、初期の節税効果が高くなります。例えば、取得価格600万円の車両に対して定率法を適用すると、初年度は償却額が多く、後年度に向けて徐々に償却額が少なくなります。
| 項目 | 定額法 | 定率法 |
| 方法 | 毎年一定の金額を償却 | 車両の帳簿価額に対して一定の償却率を掛けて償却 |
| 償却額 | 毎年同じ金額が償却される(均等償却) | 初期の年で大きな償却額が計上され、後年は少なくなる |
| メリット | 予算管理がしやすく、毎年同額を計上 | 初期の節税効果が大きい |
| デメリット | 節税効果が長期間で分散される | 初期段階での償却額が大きく、後半に減少する |
| 適用例 | 取得価格を耐用年数で割って償却金額を決定 | 取得価格に償却率を掛けて毎年の償却額を計算 |
リースの場合の計算方法
リース車両の場合、減価償却は行われません。リース契約に基づいて支払うリース料が全額経費として計上されます。したがって、リース車両の税務上の取り扱いは、購入した場合とは異なります。
リース契約におけるリース料は、支払いが発生した年度に全額経費として計上できます。リース契約は通常、月額の定額払いであり、リース料は契約期間中にわたって均等に分けて経費として認識されます。
| 項目 | メリット | デメリット |
| 経費計上の方法 | リース料全額が経費として計上され、初期費用が軽減される | リース契約終了後に車両を所有できない |
| 予算管理 | 月々のリース料が一定で予算管理がしやすい | 長期的に見るとリース料の総額が高くなる可能性がある |
| 初期費用 | 初期費用がほぼ不要で、資金繰りが安定しやすい | 車両の所有権がリース会社にあるため、自由な変更や改造ができない |
| 経費処理の簡便さ | 減価償却の手続きが不要で、全額経費処理が簡単 | リース料支払いが続く限り、経費計上が続き、最終的なコストが膨らむ可能性がある |
例えば、月額5万円のリース料を支払い、契約期間が3年の場合、リース料5万円×12ヶ月×3年=180万円を全額経費として計上できます。また、リース車両の場合、維持費(ガソリン代や保険料など)や修理費用についても、事業用の割合を按分して経費計上が可能です。
新車と中古車の減価償却の違い
車を事業用に購入する場合、減価償却は重要な節税手段です。新車と中古車では、減価償却の計算方法や期間が異なります。
新車を購入した場合、その減価償却は法定耐用年数に基づいて行われます。普通自動車は6年、軽自動車は4年が法定耐用年数として定められており、購入価格に対して均等に減価償却が行われます。例えば、新車の普通車を600万円で購入した場合、6年間にわたって毎年100万円ずつ経費計上することになります。
中古車を購入した場合、減価償却の期間は法定耐用年数を基準にしますが、実際には購入時の年式や車の状態によって、償却開始年数が短くなることがあります。例えば、4年落ちの普通車を購入した場合、耐用年数は通常6年ですが、償却開始年数はその年式に基づいて調整され、実質的には4年間程度で減価償却が終了する場合が多いです。このため、中古車の減価償却は新車よりも早く節税効果を得ることが可能となります。
中古型落ち4年がベスト?
中古車を購入する際、特に「型落ち4年」がベストな選択肢としておすすめされることがあります。その理由は、減価償却の観点から見ても、コストパフォーマンスが優れているからです。型落ち4年の車は、新車購入時の価格より大幅に値段が下がっており、購入価格に対する減価償却のメリットが大きくなります。
例えば、4年落ちの車を購入することで、減価償却の開始年数が短縮され、同じ金額であれば、新車よりも早く経費として計上できるメリットがあります。このような中古車を選ぶことにより、初期費用を抑えつつ、減価償却期間も短縮され、早期に節税効果を得られるため、特に事業を始めたばかりの方や、早期に経費を計上したい方にとって非常に有利です。
CHECK
・事業用車の取得費用は経費になるが、減価償却で数年に分けて計上が必要がある
・減価償却は法定耐用年数に応じて行う必要があり、新車と中古車で期間が異なる
・車両費は高額であるため、減価償却という形で数年にわたり経費計上する必要がある
車の維持費はどこまでが経費?
経費として計上できる車関連のもの・ならないもの
車を事業用に使う場合、その維持費の一部は経費として計上できますが、すべての費用が経費として認められるわけではありません。ここでは、経費として計上できるものとできないものを明確に区別して、適切な経費処理を行うための基準を説明します。
【経費として計上できるもの】
| 項目 | 内容 | 計上条件 |
| 自動車税・重量税 | 車の所有に伴う税金 | 事業用車のみ |
| 保険料(自賠責・任意) | 車両の保険料 | 事業用部分を按分。長期契約の場合、按分処理が必要 |
| ガソリン代 | 事業運転に使用したガソリン代 | 事業用走行分のみ経費計上。家事按分が必要 |
| 駐車場代 | 車両の駐車場代 | 事業専用の駐車場であれば全額経費計上 |
| 修理・メンテナンス費用 | オイル交換、タイヤ交換、車検費用など | 事業用部分を按分して計上 |
【経費として計上できないもの】
| 項目 | 内容 | 計上条件 |
| リサイクル料 | 車のリサイクル料金 | 経費として計上不可。資産計上 |
| プライベート使用分の費用 | 家庭での使用にかかる費用 | プライベート使用部分は経費として計上不可 |
事業用とプライベート用の按分ルール
個人事業主やマイクロ法人では、車をプライベートでも使用することが多いため、全額を経費にすることはできません。そのため、家事按分を行い、事業使用分のみ経費として計上する必要があります。
【按分方法の例】
| 按分方法 | 内容 | 計上方法 |
| 走行距離按分 | 年間走行距離のうち、事業用の走行距離に基づく按分 | 例えば、年間10,000km走行し、6,000kmが事業用の場合、60%を経費に計上 |
| 使用日数按分 | 使用日数のうち、事業用の日数に基づく按分 | 例えば、月間20日間使用し、そのうち12日間が事業用の場合、60%を経費に計上 |
また、ガソリン代や保険料、駐車場代なども事業用とプライベート用で分けて処理する必要があります。税務調査の際に説明できるよう、走行記録を残しておくことが重要です。
CHECK
・車の維持費は多岐にわたり、それぞれ適切な勘定科目で経費計上する必要がある
・事業用とプライベート用の車を併用する場合、家事按分で事業使用分のみ経費計上可能
・税務調査に備え、走行記録などの客観的な証拠を残すことが重要
「購入」と「リース」、どちらを選ぶべきか?
車を取得する際、「購入」と「カーリース」どちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。それぞれの特徴を比較しながら、事業主に適した選択肢を見ていきます。
「購入」と「リース」の違い
| 項目 | 購入 | カーリース |
| 所有権 | 事業主が持つ | リース会社が持つ |
| 初期費用 | 高い(頭金・登録費用など) | ほぼ不要 |
| 月々の支払い | なし(ローンの場合あり) | 定額で支払う |
| 減価償却 | 必要(耐用年数あり) | 不要(リース料は全額経費) |
| 経費計上 | 減価償却+維持費 | 毎月のリース料全額 |
「購入」がおすすめの人
以下に当てはまる場合は、車を購入する方がメリットが大きいです。
- 長期間(6年以上)同じ車を使いたい人
- 中古車を購入し、短期間で減価償却したい人
- 走行距離制限がない方がよい人(リースは距離制限がある場合が多い)
- カスタマイズを自由にしたい人(リース車は改造不可が多い)
「カーリース」がおすすめの人
以下のような場合は、カーリースを選ぶとメリットが大きいでしょう。
- 初期費用を抑えたい人(頭金や登録費用が不要)
- 毎月の経費を一定にしたい人(資金繰りが安定する)
- 減価償却の手続きを避けたい人(リースなら処理が簡単)
- 最新の車に定期的に乗り換えたい人(リース期間終了後に新しい車へ)
例えば、「事業が成長段階にあり、初期費用を抑えつつ経費計上をスムーズにしたい」という場合、カーリースが有利です。一方で、「中古車を購入して早く減価償却を終えたい」なら、購入が向いています。
CHECK
・車の取得方法は購入とリースがあり、それぞれ所有権や初期費用、経費計上などに違いがある
・長期間の利用やカスタマイズを希望する場合は購入が、初期費用を抑えたい場合はリース
・事業の状況や車の利用目的によって、購入とリースどちらが適しているか検討する必要がある

個人事業主やマイクロ法人にとって、車は重要な節税ツールです。購入なら減価償却による節税、リースなら全額経費化が可能。さらに、ガソリン代や保険料などの維持費も適切に計上することで、経費を最大限活用できます。事業スタイルに合った取得方法を選び、節税効果を最大化しましょう。適切な経費処理が、資金繰りの安定と事業成長につながります。