賢く節税!マイクロ法人のための共済ダブル活用術
- Home
- フリーランスの資金術
- 賢く節税!マイクロ法人のための共済ダブル活用術
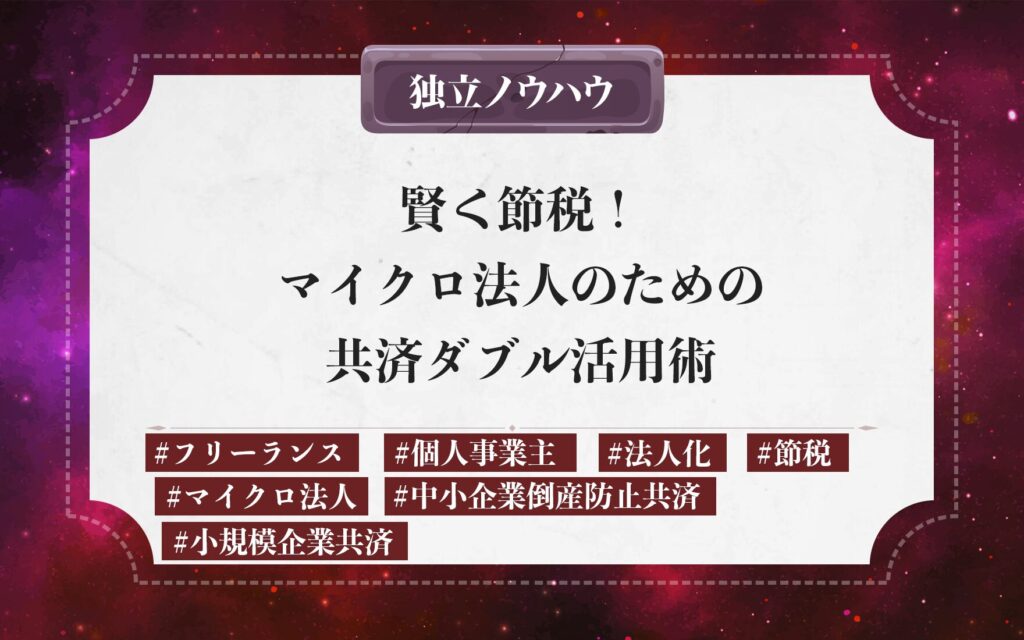
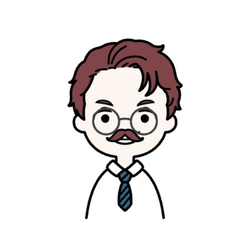
フリ転編集部 山脇
大手新聞社で編集オペレーターを務めた後、奈良日日新聞社に入社し、制作課主任として編集業務全般(紙面組版をはじめ、記者・広告制作、デザイン業務など)に従事。休刊後はフリーランスとして本格的に活動を開始し、新聞組版のほか、地方紙やウェブメディアでの原稿執筆も行う。
マイクロ法人の経営者にとって、税負担の軽減と資金繰りの安定は重要な課題です。その解決策として注目されるのが「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」と「小規模企業共済」です。本記事では、これらの制度の概要とメリット、さらに両制度を活用することで得られる節税効果について詳しく解説します。

経営セーフティ共済と小規模企業共済の併用は、マイクロ法人にとって効果的な節税策です。しかし、経営セーフティ共済は解約時に課税されるため、単なる税の繰り延べに過ぎません。長期的な視点で計画的に活用し、将来の資金準備と税負担のバランスを最適化することが重要です。
目次
経営セーフティ共済とはマイクロ法人の強い味方
経営セーフティ共済の概要とメリット
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先が倒産した際の資金繰りを支援する制度です。掛け金は月額5,000円から20万円まで設定可能で、最大800万円まで積み立てることができます。 主なメリットとして、掛け金の全額を損金算入できるため法人税の節税効果があること、万が一の際には低利で借入が可能であること、最大40カ月分の共済金貸付が受けられることが挙げられます。
加入条件と注意点
経営セーフティ共済に加入できるのは、1年以上の事業実績がある法人または個人事業主です。マイクロ法人も条件を満たせば加入できますが、解約時の課税や掛け捨てのリスクを考慮する必要があります。
| 内容 | |
| 加入対象 | 1年以上の事業実績がある法人または個人事業主 |
| 掛け金 | 月額5,000円~20万円(最大800万円まで積立可能) |
| 解約時のリスク | 12カ月未満で解約すると掛け捨てになる |
| 税務上の注意点 | 解約時の返戻金(解約手当金)は益金として課税対象 |
| 活用のポイント | 解約時の税負担を考慮し、計画的に活用する |
解約時の返戻金(解約手当金)は益金として課税対象となるため、解約のタイミングによって税負担が発生する可能性があります。この制度は税負担を先送りする仕組みであるため、解約時の対応が重要です。
CHECK
・取引先倒産時の資金繰りを支援する制度
・掛け金は損金算入可能で、節税効果がある
・解約時の税負担を考慮した利用が重要
小規模企業共済とは? 長期的な節税効果を得る仕組み
小規模企業共済の概要とメリット
小規模企業共済は、個人事業主や法人の役員が退職金を準備できる制度です。月額1,000〜70,000円の掛け金を積み立て、将来的に退職金として受け取ることが可能です。掛け金が全額所得控除となるため、所得税・住民税の節税効果が得られます。 また、退職金として受け取る際には税制優遇があるため、事業廃止時や退職時の生活資金としても活用しやすいのが特徴です。
加入条件と注意点
小規模企業共済は、一定の従業員規模以下の個人事業主や法人役員が対象です。業種によって適用条件が異なるため、事前に確認が必要です。また、事業を廃止しない限り解約できない点にも注意が必要です。
| 業種・組織 | 加入資格(条件)および対象者 |
| 建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業 | 常時使用する従業員が20人以下の個人事業主または会社役員(共同経営者も可、ただし個人事業主1人につき2人まで) |
| 商業(卸売業・小売業)・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 常時使用する従業員が5人以下の個人事業主または会社役員(共同経営者も可) |
| 企業組合・協業組合 | 常時使用する組合員または従業員の数が20人以下の役員 |
| 農事組合法人(農業の経営を主としている) | 常時使用する従業員の数が20人以下の役員 |
| 弁護士法人・税理士法人 | 常時使用する従業員が5人以下の社員 |
解約金の取り扱い
小規模企業共済は、一定の従業員規模以下の個人事業主や法人役員が対象です。業種によって適用条件が異なるため、事前に確認が必要です。また、事業を廃止しない限り解約できない点にも注意が必要です。
退職や廃業に伴う解約で受け取る共済金は「退職所得」として扱われ、退職所得控除が適用されるため、税負担を軽減できます。一方、任意解約の場合は「一時所得」として計算されるため、課税対象額が大きくなり、税負担が重くなる可能性があります。また、加入期間が短い場合は返戻率が低く、元本割れするリスクもあります。特に、20年未満の解約では返戻率が大幅に下がるため、長期的な運用を前提に加入することが重要です。
また、この制度は退職金としての活用を前提とした長期的な資金計画が求められるため、途中解約を避けるための資金計画が必要です。
CHECK
・個人事業主や役員が退職金を準備できる制度
・掛け金が全額所得控除となり、高い節税効果がある
・事業廃止時まで解約できないため、注意が必要
両制度を活用することで得られる節税効果
両立のメリット
経営セーフティ共済と小規模企業共済を併用することで、短期と長期の両面から節税と資金準備が可能になります。経営セーフティ共済では法人税を節税でき、小規模企業共済では個人の所得税を抑えることができます。
節税例
例えば、年間の利益が500万円あるマイクロ法人が両制度を活用する場合、以下のような節税効果が期待できます。
| 掛け金 | 節税効果 | |
| 経営セーフティ共済 | 年間240万円(20万円×12カ月) | 法人税の課税所得が減少 |
| 小規模企業共済 | 年間84万円(7万円×12カ月) | 役員報酬から所得控除され、個人の税負担が軽減 |
このように、法人・個人の両方で税負担を抑えながら、将来の資金準備が可能になります。
両立の際の注意点
経営セーフティ共済は解約時に課税されるため、一時的な税負担が増える可能性があります。小規模企業共済は退職や事業廃止時の活用を前提とするため、長期的な視点での資金計画が必要です。
短期的な節税効果だけでなく、将来的な資金管理を考慮して両制度を活用することが重要です。
CHECK
・両制度併用で法人・個人の税負担を軽減できる
・具体的な掛け金で節税効果と資金準備が可能になる
・解約時の課税や長期計画を考慮した利用が重要

マイクロ法人にとって、経営セーフティ共済と小規模企業共済は強力な節税ツールです。短期的な法人税の削減には経営セーフティ共済、長期的な所得税対策には小規模企業共済が有効です。ただし、両制度とも解約時の税負担に注意が必要なため、計画的に活用することが大切です。戦略的な資金管理を行い、税負担を最適化しましょう。