検索AIで情報収集「信頼性・拡張性があり業務効率化に“使える”ツール」正解はどれ?
- Home
- フリーランスの時短術
- 検索AIで情報収集「信頼性・拡張性があり業務効率化に“使える”ツール」正解はどれ?
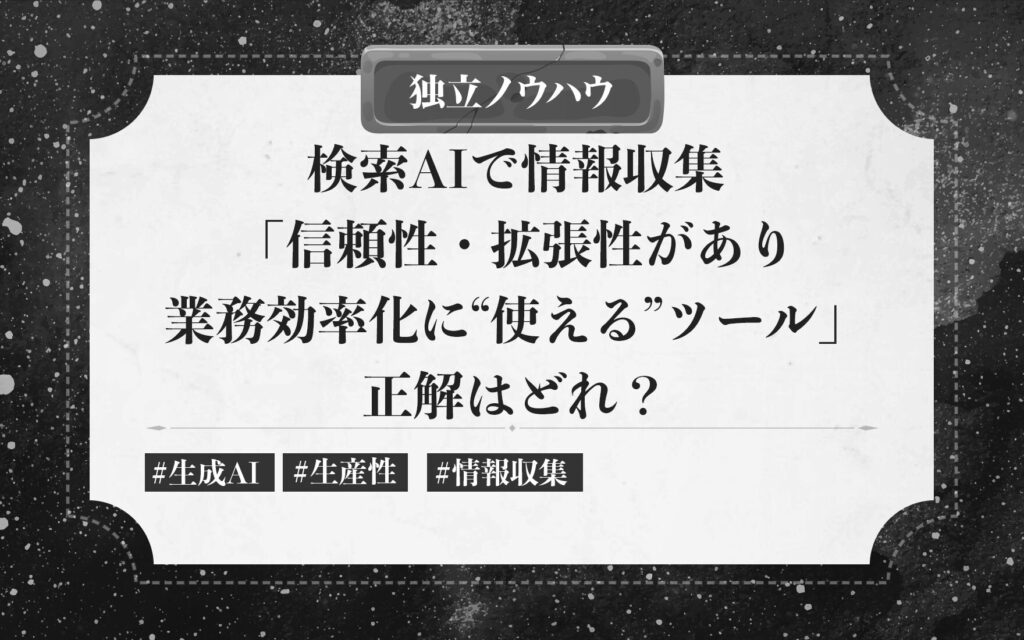
フリ転編集部
「フリ転」は、フリーランスクリエイター向けのコミュニティメディアです。 デザイナー・ライターやエンジニア・マーケターなどクリエイティブな冒険心を持つ仲間と、独立ノウハウ&最新ツール情報や著名人インタビューなど、豊富なコンテンツを提供します。
昨今、さまざまな業務がAIによって効率化されていますが、「情報収集」もその1つです。
ネット空間に存在する膨大な量の情報やデータの海から、必要なものを探してピックアップし、まとめるのは大変な作業ですが、AIを活用すればその手間をかなり省くことができます。
ただし、AIによる情報収集ツールを使う際には、「集められた情報は本当に正確なのか」「欲しい内容がきちんと網羅されているか」「情報が使いやすい形にまとめられているか」といった部分が気になるところです。
今回は、主なAI情報収集ツールを取り上げ、上記のようなポイントも考慮しながら、そのメリット・デメリットや使い勝手について検証していきます。
目次
検索AIは情報収集の業務を効率化するアシスタント
生成AIについて情報発信をしている「TomoAI」さんのnote記事『検索AIで情報収集をレベルアップ!Perplexity, Genspark, Feloを徹底比較』では、情報収集に使う「検索AI」について、「簡単に言うと、検索AIは、みんなが普段使っている検索エンジンの進化版みたいなもの」と説明しています。
従来の情報収集は、自分でインターネット検索をして、表示された検索結果を1つずつ確認し、情報をまとめる必要がありました。その点、検索AIは質問をするだけで適切な情報を探索してまとめてくれるので、情報収集が効率化されます。
キーワードを駆使して自分で情報を探す手間が省け、AIが最適な答えを見つけてくれるという、優秀なアシスタントのような存在といえます。
情報収集の専門ツール
ここからは、検索AIについて、まず「情報収集の専門ツール」として開発された代表的なサービスをピックアップします。
ビジネスや学術分野での情報収集やコンテンツ作成をサポートするPerplexity AI。情報ソースをAIが分析し、迅速なファクトチェックを可能にするGenspark。そしてプレゼン資料作成やマインドマップ生成を支援する機能を備えたFelo AIの3つです。
情報の信頼性が確認しやすいか、業務効率化や生産性向上に貢献してくれるか、といった実際の使い勝手を想定しながら、検証していきます。
複数の引用元から関連する情報をまとめて教えてくれる「Perplexity AI」
まず、情報収集の専門ツールとして取り上げるのはPerplexity AIです。従来の検索エンジンなどと異なり、ユーザーの質問に対してAIがWeb上の膨大なデータから最適な情報を抽出し、要約して提供してくれる点が特徴です。
ビジネスでのリサーチから、コンテンツ作成の準備、学術論文の調査など、さまざまなシーンで活用できるAIツールです。
AIの活用事例や最新情報の調査と検証を行っている「AI-Bridge Lab(エーアイブリッジラボ)」のnote記事『【Perplexity】生成AI検索で情報収集の質とスピードが大幅アップ!』では、主なメリットとして、迅速な回答の提供、引用元の表示、多言語対応、無料で利用できる点が挙げられています。
一方で、専門的な分野での精度や情報収集の範囲には課題もあるとのこと。
「ハヤシ シュンスケ」さんのnote記事『【初心者向け】Perplexity AIの使い方を完全解説!AI検索エンジンで情報収集を効率化』では、Perplexity AIについて「検索バーに質問を入力するだけで回答と情報源がまとめて表示され、従来の検索エンジンのように検索結果を一つ一つ開く手間が省ける」と評価しています。
検索結果をまとめて保存するコレクション機能や、有料のPro版で利用できる画像・ファイル分析など、高度な機能もメリットとして紹介されています。
「むろしょう@ひとり旅好きのKindle作家」さんのnote記事『Googleを超えた情報収集AI「Perplexity」の使い方とは?ChatGPTだけじゃない生成AI』では、ChatGPTとの違いについても語られています。ChatGPTが広範』なトピックに対応した対話型のツールで、創造的なアイデアや会話を提供するのに対し、Perplexity AIは情報収集に特化し、Web上の最新情報を自動で集約、リサーチの効率化に優れているとしています。
ファクトチェックの手間が大きく省ける「Genspark」
続いて取り上げる情報収集専門ツールはGensparkです。2023年に登場した次世代のAI検索エンジンで、対話形式で質問を受け付け、検索結果に基づいて自動的にSparkpagesと呼ばれるカスタムページが生成されます。このページには、AIが収集・整理した関連情報が表示され、チャットウィンドウに追加の質問を入力して、情報を深掘りすることもできます。
ヒト起点のマーケティング×デザインでビジネスを前進させる企業「CUEBiC(キュービック)」のnote記事『検索AIの金字塔なるか!?Gensparkのファクトチェック機能が凄すぎた』では、Gensparkのファクトチェック機能が特に評価されています。
AIが情報の正確性を自動的にチェックし、情報源に記載された文章を分解して個別に検証することで、誤情報を特定しやすくしているとのこと。
これにより、従来の検索エンジンによるリサーチではユーザー自身が参照元へアクセスして行う必要があったファクトチェックが簡素化できます。Gensparkでは、引用した部分をスクリーンショットしてくれるため、ユーザーが引用元へアクセスする面倒がなく、大幅な時間短縮になります。
デメリットとしては、モバイルアプリが未提供である点と、現在(2025年1月)は全機能が無料であるものの今後は何らかの制限や有料メニューが設定される可能性がある点が指摘されています。
情報収集だけでなく資料作成までカバーする日本発のAIツール「Felo AI」
最後の専門ツールはFelo AI、日本発のAI検索エンジンです。単なる検索機能を超え、情報収集から資料作成までを効率化することができる点が大きな特徴で、膨大なデータベースから関連性の高い情報を瞬時に取得し、自動で要約やプレゼン資料を生成することができます。
イノベーティブジャパン代表取締役の「浅見純一郎」さんのnote記事『Felo AI検索エンジン完全ガイド:ビジネスに役立つ情報収集と資料作成の新常識』では、Felo AIの主な機能として情報収集に加えて、プレゼン資料作成とマインドマップ生成が紹介されています。
情報収集機能は、学術論文などから迅速にデータを収集し要約して提供するため、従来の検索エンジンよりも効率的だと評価しています。
このほか、プレゼン資料の作成機能では検索結果を基に自動でスライドが生成され、マインドマップ機能では情報同士の関連性を視覚的に整理してくれるので、業務の効率化が期待できると紹介。市場分析、リサーチ、コンテンツ制作などビジネスシーンでの活用にマッチしやすいといえるでしょう。
Felo AIは基本機能が無料で利用でき、有料プランではさらに多機能が提供されます。今後、ビジネス環境での重要なツールとして、さらに進化することが期待されます。
情報収集専門ツールは一長一短
ここまで3つの「情報収集専門ツール」を見てきました。それぞれに強みとなる特徴があり、どんな使い方や要件を求めているかによって、ベストといえるツールが変わってくるように思われます。
引用元も含めて収集した情報を表示する「一覧性」を重視するならPerplexity AI、情報の正確性とファクトチェックの効率化を求めるならGenspark、プレゼン資料やマインドマップの作成といった「情報収集後の工程」までを見据えるならFelo AIにそれぞれ強みがあり、ニーズによって使い分けても良さそうです。
汎用プラットフォーム系のツール
続いて、汎用プラットフォームが提供するサービスを情報収集ツールとして応用する場合を検証していきます。
ビジネスや学習、創作活動の効率化を進める強力なAIツールとしてGoogleが提供しているGemini 2.0と、Microsoft×Open AIの検索エンジン搭載チャットツールBing AIです。これらが情報収集のツールとしても使えるのか、収集の精度や拡張性も含めて見ていきます。
Google発のAI「Gemini 2.0」は情報収集機能も充実
汎用プラットフォーム系のツールとしてまず取り上げるのはGemini 2.0です。Googleが開発した次世代AIモデルで、サブスクリプションプランであるGemini Advancedで提供されています。
テキスト、画像、動画、音声、コードなど多彩な情報を統合して処理できる「マルチモーダル」対応が特徴で、長大なデータを一気に解析する圧倒的な処理能力を持っています。
IT企業のエンジニアをしている「###dalhi###」さんのnote記事『Google発の次世代マルチモーダルAI『Gemini2.0』徹底解説:Deep Research搭載で情報収集を劇的効率化!』では、このGemini 2.0を情報収集の観点からも検証しています。ChatGPTのように膨大な情報の要約や解析ができるだけでなく、「Deep Research」というAI検索機能により、莫大な時間を費やしていた情報収集作業がかなり効率化されるといいます。
これは大量のWebサイトから一括で情報を収集し、参照元もリスト化するもので、要約レポートも自動で生成してくれます。膨大な数のサイトを1つずつ巡回する手間が省け、リサーチや資料作成にかかる時間が大幅に短縮されます。ただし、Deep Researchは今のところ英語版で利用可能な機能のため、日本語による情報ソースの探索には課題がありそうです。
もう1つ、Gemini 2.0のメリットとしてはGmailやGoogleドライブなどGoogleエコシステムとの連携がしやすい点が挙げられています。収集した情報をGoogleドキュメントやスプレッドシートに直接出力でき、業務の効率化に大きく貢献してくれます。
Microsoft×Open AIの検索エンジン内蔵ツール「Bing AI」
汎用プラットフォーム系のツールとして、次にBing AIを紹介します。Microsoftの検索エンジンBingにAIチャット機能を搭載したサービスで、ChatGPTと同じくOpen AI社が開発した大規模言語モデル「GPTモデル」が採用されています。
株式会社バーグハンバーグバーグのライター「品田遊(ダ・ヴィンチ・恐山)」さんのnote記事『Bing AIのチャットができること』では、Bing AIのチャット機能でさまざまなコンテンツ生成を試したテストの様子が紹介されています。
ジョークや俳句を考えさせる、漫才や裁判などシチュエーションを設定してロールプレイをさせてみる、おじさん構文やラップバトル、なぞなぞなど、特定のフォーマットの中で文章を生成させる、といったテストを実施して、「かなり高度に文脈を読めている」と評価しています。
一方で、「情報収集よりも文章形成が中心では」とも指摘しています。
実際には、Bing AIは文章や画像などの生成ができるだけでなく、情報収集の機能も持ち合わせています。Bing AIに質問を入力すると、回答とともにその根拠となるサイトのURLが表示されます。時事ネタや天気についての質問に対してもリアルタイムの情報が表示される特徴があります。
Bing AIが参照したWebサイトが明記されることでデータのソース・出典を簡単に確認でき、情報の正確性が検証できるものの、ユーザーがソースのURLにアクセスするという手間はある程度考慮する必要がありそうです。
また、収集した情報の出力方法も箇条書きや表などが指定できますが、そのままプレゼン資料を生成するといったシームレスな連携はまだ弱いといえます。
プラットフォーマー対決はGoogleが一歩リードか
Google発のAIツールであるGemini 2.0とMicrosoft×Open AIによるBing AIを見てきましたが、情報収集という観点に絞った場合はGemini 2.0が優れているように思われます。
参照元も含めて要約レポートを自動生成してくれるDeep Researchの存在がやはり大きく、サイト巡回にかかる時間と労力の削減は大きな魅力です。
Googleドライブ、ドキュメント、スプレッドシートなどとの連携でデータの扱いがよりスムーズになる点も、作業の効率化に貢献するでしょう。
対して、Bing AIは基本的にはAIチャットツールと考えるべきで、情報収集ツールとしても使えるものの、情報ソースへのアクセスや資料生成などの拡張性においては情報収集の専用ツールに及ばないのが現状といえます。
情報収集ツールAIのまとめ
今回はAIによる情報収集ツールを5つ見てきました。実際にビジネスやアカデミックなシーンで正確かつ網羅的なリサーチを行うとなると、やはりプラットフォーム系のツールよりは専用ツールとして開発・提供されているサービスの方が優れているといえるでしょう。
もちろん、それほど求められるレベルがシビアではなく、日常的な検索行動の延長として何かについて少し詳しく調べたいというニーズであれば、プラットフォーム系のツールも十分に恩恵を与えてくれる存在です。慣れ親しんだプラットフォームの中でそのまま利用できる点もメリットとなります。
自分がどんなレベルの情報収集を求めているのか、そしてツールごとの得意不得意を吟味しながら、最適なツールを選んでみてください。