給料を渡して、税金もカット!?フリーランス家族の最強節税法
- Home
- フリーランスの資金術
- 給料を渡して、税金もカット!?フリーランス家族の最強節税法
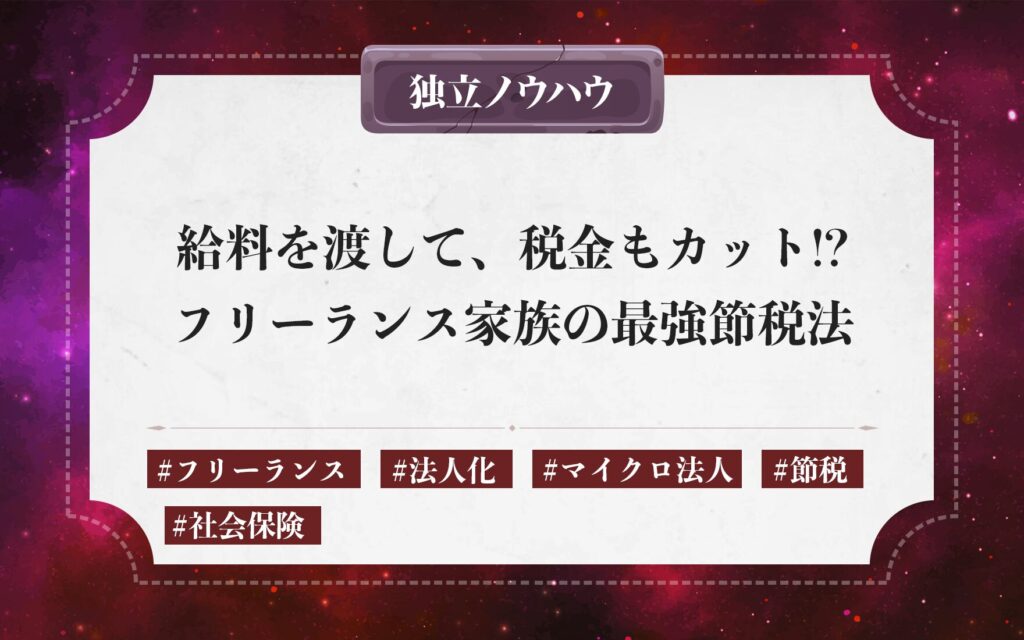
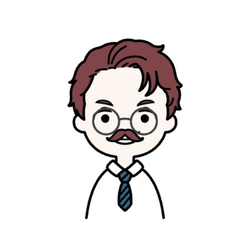
jpndesft
大手新聞社で編集オペレーターを務めた後、奈良日日新聞社に入社し、制作課主任として編集業務全般(紙面組版をはじめ、記者・広告制作、デザイン業務など)に従事。休刊後はフリーランスとして本格的に活動を開始し、新聞組版のほか、地方紙やウェブメディアでの原稿執筆も行う。
個人事業主やフリーランスとして活動される方の多くは、配偶者や家族の協力を得ながら事業を運営されています。こうした家族の労働に対して正当な報酬を支払い、かつ節税効果も得られる制度が「専従者給与」や「専従者控除」です。しかし、「いくらまで支払えるのか」「どのような手続きが必要か」など、わからないことも多いのではないでしょうか。
この記事では、青色申告と白色申告それぞれの専従者給与・控除の仕組みや上限額、節税効果について詳しく解説します。
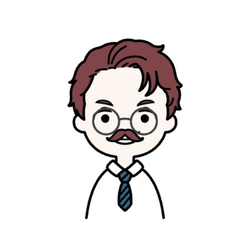
専従者給与は家族経営の強みを生かす制度です。適正な金額設定と勤務実態の明確な記録が不可欠です。毎月の勤務記録表を作成・保管し、業務内容と時間を具体的に記録しましょう。これにより税務調査にも対応でき、適切な節税効果が得られます。
目次
青色申告事業専従者給与・専従者控除の基本
専従者給与・専従者控除の仕組み
専従者給与とは、個人事業主が事業に従事する家族(専従者)に支払う給与のことです。青色申告では「青色事業専従者給与」、白色申告では「事業専従者控除」という形で税制上の優遇を受けることができます。
両者の大きな違いは以下の表のとおりです。
| 区分 | 青色申告(青色事業専従者給与) | 白色申告(事業専従者控除) |
| 対象者 | 生計を一にする配偶者や親族 | 生計を一にする配偶者や親族 |
| 控除額 | 実際に支払った金額(適正な金額) | 配偶者:86万円その他親族:50万円(定額) |
| 届出 | 青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要 | 不要 |
| 専従者の所得税 | 専従者が確定申告する必要あり | 課税対象外のため確定申告不要 |
専従者の条件
専従者として認められるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 事業主と生計を一にする配偶者またはその他の親族であること
- 年齢が15歳以上であること(年の途中で15歳になる場合は、誕生日以降が対象)
- その年を通じて6か月を超える期間、専ら事業に従事していること
ここでいう「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はなく、例えば学生の子どもに仕送りをしている場合なども含まれます。また「専ら事業に従事」とは、主にその事業のために働いていることを意味し、パートタイムでも条件を満たせば専従者として認められます。
専従者給与の上限額
青色申告の専従者給与には、明確な上限額の規定はありませんが、「適正な金額」であることが求められます。この「適正な金額」は、以下の要素を考慮して決定されます。
- 専従者の従事した期間
- 従事した時間(労働時間)
- 従事した内容(業務内容)
- 事業の規模や収益性
- 同業種・同地域の給与水準
一般的な目安としては、同じ業務を行う一般従業員の給与水準と比較して妥当と思われる金額、または事業所得の50%程度までが安全圏とされています。
以下は業種別の専従者給与の一般的な相場です(あくまで参考値)
| 業種 | 月額給与の目安 | 年間給与の目安 |
| 小売業 | 15~25万円 | 180~300万円 |
| サービス業 | 15~25万円 | 180~300万円 |
| 建設業 | 20~30万円 | 240~360万円 |
| IT・フリーランス | 15~30万円 | 180~360万円 |
専従者給与と専従者控除の使い分け
専従者給与と専従者控除を使い分ける際には、いくつかのポイントを考慮すると良いでしょう。
まず、青色申告における専従者給与は、実際に支払った金額が経費として認められるうえ、上限についても比較的柔軟です。一方、白色申告の専従者控除は、定額での控除となるため手続きが簡便という利点があります。
また、専従者自身の所得状況によって、世帯全体の税負担が変動する可能性もあるため、その点も踏まえて検討する必要があります。
CHECK
・専従者給与と控除の違いを理解して制度を使い分ける必要がある
・専従者と認められるための条件を満たすことが重要
・給与額は業務内容や相場を参考に適正に設定するべき
専従者給与・専従者控除の節税効果と必要手続き
青色申告における節税効果
青色申告事業専従者給与の最大の魅力は、家族の働きに応じた給与を経費として計上できる点です。これにより事業主の所得を専従者に分散させ、全体の税負担を軽減することができます。
具体的な節税効果を見てみましょう。
【例】年間所得800万円の個人事業主が配偶者に専従者給与として年間240万円を支払う場合
| 項目 | 専従者給与なし | 専従者給与あり | 差額 |
| 事業主の所得 | 800万円 | 560万円 | ▲240万円 |
| 事業主の所得税・住民税(概算) | 約207万円 | 約121万円 | ▲86万円 |
| 専従者の所得 | 0円 | 240万円 | 240万円 |
| 専従者の所得税・住民税(概算) | 0円 | 約24万円 | 24万円 |
| 合計税負担 | 約207万円 | 約145万円 | ▲62万円 |
※税額は基礎控除や社会保険料控除などを考慮した概算値です。
このように、高所得の事業主から低所得の専従者へ所得を移転することで、累進課税の効果により全体の税負担を軽減できます。
白色申告における専従者控除
白色申告の場合は、実際の給与支払いに関係なく、以下の定額を控除できます。
- 配偶者:86万円
- その他の親族:1人につき50万円
【例】年間所得500万円の個人事業主が配偶者を専従者とする場合
| 項目 | 専従者控除なし | 専従者控除あり | 差額 |
| 事業主の所得 | 500万円 | 414万円 | ▲86万円 |
| 事業主の所得税・住民税(概算) | 約104万円 | 約80万円 | ▲24万円 |
白色申告の場合、専従者への実際の給与支払いは必要なく、また専従者側に課税されることもありません。手続きも簡単ですが、控除額が固定されているため、節税効果は青色申告に比べて限定的です。
専従者給与に必要な手続き
青色申告で専従者給与を計上するためには、以下の手続きが必要です。
- 青色事業専従者給与に関する届出書の提出
- 提出期限:その年の3月15日まで(新規事業開始時は開業届と同時)
- 提出先:所轄の税務署
- 給与の適正な支払いと記録
- 毎月定期的に専従者の銀行口座等に振り込み
- 給与台帳の作成・保管
- 源泉徴収(必要な場合)
- 専従者の確定申告
- 専従者本人が給与所得として確定申告(必要な場合)
専従者給与額の変更方法
事業の状況変化や専従者の業務内容の変更に応じて、専従者給与の金額を変更したい場合は、以下の手続きが必要です。
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」の再提出
- 変更適用年の3月15日までに提出
- 年の途中での変更の場合
- 原則として認められませんが、以下の場合は例外的に可能
- 業務内容の著しい変化があった場合
- 物価の著しい変動があった場合
- 専従者の病気・出産等による就労時間の変化があった場合
- 原則として認められませんが、以下の場合は例外的に可能
給与額の変更は税務調査で特に注目される点ですので、変更の合理的な理由を記録しておくことが重要です。
CHECK
・青色申告では所得分散により節税効果が得られる
・白色申告は手続きが簡単だが控除額に限りがある
・専従者給与の適用や変更には届出と記録が必要になる
税務調査対策と専従者給与の活用法
税務調査での注意点
専従者給与は税務調査でよく確認される項目の一つです。以下の点に注意しましょう。
- 専従者の実際の従事状況の証明
- 勤務表やタイムカードなどの労働記録を保管
- 業務日誌や議事録に専従者の参加を記録
- 専従者が担当した業務の成果物の保存
- 給与の適正額の証明
- 同業他社の給与水準の資料
- 専従者の職務内容や技能を示す資料(資格証明書など)
- 事業への貢献度を示す資料
- 給与の実際の支払いの証明
- 給与振込の銀行明細
- 給与台帳
- 源泉徴収票や支払調書
専従者給与を適正に計上するためには、専従者の就業実態を客観的に証明できる記録が必要不可欠です。以下に、税務調査でも通用する「専従者勤務記録表」のサンプルをご紹介します。このような記録表を日々つけることで、専従者の業務内容や労働時間を明確に示すことができます。いざという時の証拠資料として、ぜひ参考にしてください。
| 専従者勤務記録表(サンプル)事業者名: 山田太郎専従者名: 山田花子(配偶者)年 月: 2025年4月 | |||
| 日付 | 勤務時間 | 勤務内容 | 備考 |
| 4/1(月) | 9:00-15:00 (6h) | 経理処理、請求書発行 | 請求書10件処理 |
| 4/2(火) | 9:00-17:00 (8h) | 顧客対応、資料作成 | 新規顧客2件対応 |
| 4/3(水) | 9:00-16:00 (7h) | WEB更新、SNS運用 | Instagram投稿5件 |
| 4/4(木) | 休業 | – | – |
| 4/5(金) | 9:00-17:00 (8h) | 在庫管理、発送業務 | 商品発送15件 |
| 4/6(土) | 10:00-15:00 (5h) | イベント出店補助 | 売上85,000円 |
| 4/7(日) | 休業 | – | – |
| (中略) | |||
| 4/30(火) | 9:00-17:00 (8h) | 月次集計、翌月準備 | 月間報告書作成 |
| 合計 | 140時間 | ||
| 給与金額: 200,000円(月額) 振 込 日: 2025年5月25日振込先口座: ○○銀行△△支店 普通口座1234567事業主確認: 山田太郎 ㊞ 専従者確認: 山田花子 ㊞ | |||
税務調査で最も重要なのは「実態があること」です。形式的な手続きだけでなく、専従者が実際に働いていることを示す証拠を日頃から蓄積しておきましょう。
青色専従者給与と配偶者控除の違い
青色専従者給与と配偶者控除は、どちらも配偶者に関連する税制ですが、性質が大きく異なります。
| 項目 | 青色専従者給与 | 配偶者控除 |
| 対象 | 事業に従事する配偶者 | 所得が48万円以下の配偶者 |
| 前提条件 | 青色申告を行っていること | 配偶者の所得制限あり |
| 控除額 | 実際に支払った給与額(適正額) | 最大38万円(所得制限あり) |
| 配偶者の働き方 | 事業に従事する必要あり | 事業従事の有無は関係なし |
| 手続き | 届出書の提出が必要 | 確定申告書に記載するのみ |
どちらを選ぶかは、配偶者の働き方や事業への関与度によって判断すべきです。
専従者給与のメリットとデメリット
青色専従者給与の制度には、事業主にとっての利点と注意点の双方が存在します。具体的なメリットとデメリットは以下のとおりです。
【青色専従者給与のメリット】
- 実際の業務内容に応じた金額を経費計上できる
- 所得分散による節税効果が大きい
- 専従者の社会保険料や年金の納付実績となる
【青色専従者給与のデメリット】
- 手続きや記録の管理が必要
- 専従者側の確定申告が必要
- 税務調査のリスクがある
最適な専従者給与活用術
専従者給与の効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。制度を形式的に取り入れるだけでは十分なメリットを享受できず、むしろリスクを招く可能性もあります。以下に、専従者給与を実務の中で賢く活用するための具体的な留意点を整理しました。
- 適正な金額設定
- 業務内容に見合った給与設定
- 事業規模に応じた金額設定
- 段階的な増額で急激な変化を避ける
- 記録の徹底
- 勤務実態を示す記録の作成と保管
- 業務内容の明確化と文書化
- 給与支払いの証跡保管
- 専従者のスキルアップ投資
- 業務に関連する資格取得支援
- セミナーや研修への参加
- 専門知識の向上支援
- 将来を見据えた活用
- 専従者の社会保険加入や年金記録の確保
- 事業承継を視野に入れた役割付与
- 家族全体の資産形成戦略に組み込む
CHECK
・税務調査では実態を証明する記録が必要になる
・専従者給与と配偶者控除は適用条件が大きく異なる
・制度の活用には金額設定や記録管理が重要になる
専従者給与・専従者控除は、家族の協力を得ながら事業を営む個人事業主にとって、非常に有効な税制優遇制度です。青色申告では実際に支払った給与を経費計上でき、白色申告でも一定額の控除が認められています。
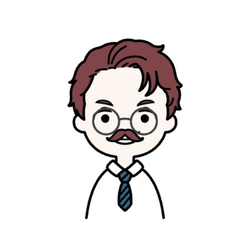
専従者給与の仕組みをしっかり理解し、税務調査にも耐えうる実態作りを心がけることで、家族経営の強みを最大限に生かしつつ、適正な節税効果を得ることができます。制度を正しく活用して、持続可能な事業運営と家族の経済的基盤の構築を目指しましょう。